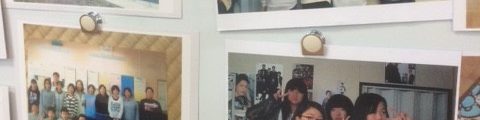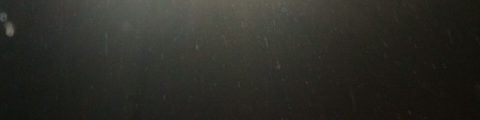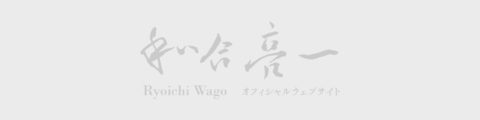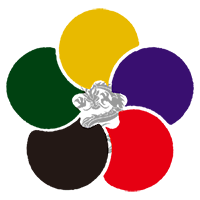〈追悼〉谷川俊太郎さん
寄 稿
星明りに独り言ちて膨らんでゆくために。
私事であるが昨年の暮れに「such and such」(思潮社)を、そして先月に「LIFE」(青土社)を、それぞれまとめることができた。詩集としては二六冊目となる。ここで足を止めずに次の創作の方針を立てなくてはとハチマキを締め直したいところである。中原中也が最初の詩「朝の歌」を書いた折に「ほゞ方針立つ。方針は立ったが、たった十四行書くために、こんなに手数がかゝるのではとガッカリす」と「詩的履歴書」に記した。
私は詩作のスタートを切った時の感慨が伝わるこの一節が好きで、時折に独り言ちている。あらためてあれこれ「手数」をかけなくてはなるまい…。手がのびる。昨年の暮れから今年にかけての谷川俊太郎をめぐる刊行物の数々を手にしてみる。新しい「方針」のヒントを少しでも、という邪心が働いている。九〇歳を超えてなおこつこつと書き続ける背中に素直に学びたいと思うのは、私のみならずではないだろうか。
谷川俊太郎・尾崎真理子の『詩人なんて呼ばれて』(新潮文庫)は、二〇一七年に刊行されたものの文庫版である。当時に読み通したが、あらためて新鮮な印象を覚える。尾崎の論考に谷川へのロングインタビューが続くという形で編まれていて、幾重もの対話が見えてくるような感じがある。
追いかけ方が実に多彩であり、質問にも文章にも新聞記者ならではの歯切れの良さがある。谷川の人生に迫ることは現代詩史をひも解くことになることをこの一冊はじっくり示してくれている。第一章「哲学者と詩人と」から始まっている。尾崎の文章の後に谷川のインタビューの「詩人になろうなんと、まるでかんがえていなかった」が続く。
哲学者である父、谷川徹三のこの文章が冒頭で引かれている。「百巻の小説より一巻の詩集である。詩は常に結晶体の緊密をもってゐる。山頂を渉る巨大な足をもってゐる。詩は常に集中であり頂点である。詩の小ささは星の小ささである。星はしかし地球より大きい」。三九歳の折に書かれたものであるとは思えない透徹したまなざしに満ちていることがこの部分だけでも分かる。
ルーツをたどるところから始まっている。父の哲学的な思考・思想を、激動の昭和の時代の暮らしのなかで、どう深く受け取ってきたのかについて随所で迫ろうとしているところがまず魅力に映った。べったりとした父子関係ではなかった様子だが、幼い頃から法政大学教授である父の蔵書や父が書いた文章や書物に親しんできた。「家庭という根から発した蒸気を受け取った雲」という尾崎のフレーズに納得させられる。
谷川はインタビューで「よく、雲を見上げているのも、全然メタファーではなくて、美しさや懐かしさがまさに迫ってきたからです。僕の究極の故郷は宇宙だという感覚を持った」と十代の頃の感性を振り返っているが、ここから現在へと至るまでに、数多の詩集を世に送り出してきたことを思えば、たくさんの星々を作り出してきたと言えるのかもしれない。「谷川宇宙」(山田兼士)の始まりである。
「詩壇の異星人」「独創を独走する」「佐野洋子の魔法」「無限の変奏」というタイトルで章立てされている。鮎川信夫らの「荒地」と戦後、大岡信らの「櫂」と五〇年代、寺山修司らと六〇年代、ねじめ正一らと七〇・八〇年代、そして現在まで、谷川という個の存在を通しながら俯瞰できる。時代の様々な波に乗りながら、一貫して語りの中で変わらないのは、自分を超えた何かと向き合う詩作の姿だ。「意識より、もっと深いところから出てきている」と谷川は河合とのある対話で述べたことが紹介されているが、そうしたものと生涯、対峙しつづけてきて、今もなおの詩作が続いていることにあらためて驚かされる。「自分を一種非情に集中した状態において、しかも言語レヴェルで考えるのではなく、言語以下というか、そういうレヴェル」と話す。先の「集中であり頂点」という父の言葉と重なる。シンプルで深い詩作への言明ならぬ星明りをいくつも見つけることが出来るだろう。
リアルタイムの谷川俊太郎…。私もまた青年となり詩を書き始めた折に、例えば教科書の詩や、アンソロジー詩集などではなく、書店で新作の詩集を初めて買い求めたのは「世間知ラズ」(思潮社・一九九三年)であった。
詩人はこの時、六十二歳である。父の死について書いた詩がこの詩集の冒頭にあるが、この詩のみならず全体が、私がこれまで読んできた谷川作品とは根本的に違う感触をもつものの集合体となり迫ってくる感じがあり、私にとって忘れられないものとなった。
山田兼士の力作「谷川俊太郎全〈詩集〉を読む」(思潮社)読む。谷川を論ずる本が昨今に増えてきた印象を語りながら「あまりに広大な谷川宇宙を十分に精査したとはとても言い難い現状だ」と序文で山田は語っている。「各詩集をできるかぎり精査し、要点をまとめることで、谷川作品の全体像を、少なくともその輪郭ぐらいは描き出したい」。
当時今よりも未熟な私ながら「世間知ラズ」に詩法の成熟と達成を見た思いを抱いたが、全ての詩集を編年の形式で網羅しているこの一冊において、この詩集の位置は、谷川の人生の第二コーナーは抜けたとしても第三コーナーにさしかかっていないあたりにあると自分なりに確かめるに至った。
還暦を迎えた詩人が自らを「世間知らず」と呼ぼうとするのは非常識な感じがあるとためらいながら受けとめたことを山田は振り返っている。「だが、その後すでに三十年の時間が流れ、今もなお〈子供〉の繊細さ素朴さを失わない、どこか、むしろ自在に操っている」とその後の仕事の歳月を俯瞰しながら語っている。
面白い点は「私はただかっこいい言葉の蝶々を追っかけただけの/世間知らずの子ども/その三つ児の魂は/人を傷つけたことにも気づかぬほど無邪気なまま/百へむかう/詩は/滑稽だ」というタイトルポエムのこの詩行を一つの宣言として受けとめているところである。「詩人の新作に触れる度に、この宣言が深く広いものとして納得できる。」と。そして「百歳で新詩集を出すときにも詩人はなお「詩は/滑稽だ」と言い切るのだろうか」と続けている。
「詩人なんて」、「世間知らず」、「滑稽だ」…などと、詩人として書くことにまつわる自己否定の言及を重ねつつも、新詩集を変わらずにこつこつと生み出し続けている詩人を「追っかけ」てきた姿が頑としてある。優れた詩人・評論家であった山田は二〇二二年に世を去った。本書の最後には「あとがきに代えて」として、翌年の秋に書かれたご長男の文章が置かれている。正に山田のライフワークであったことがうかがえる。
「晩年にこの網羅的な評論を書き終えて、父にとっては成し遂げたという思いがあったことだろう。何かと使命感に囚われたような人であったが、間違いなく父の魂は詩に救われていたし、詩がこれからも誰かの救いになってゆくことを願う」。何という胸を打つ文章だろう、と首肯した。「父の魂は詩に救われていた」という実感が頁をめくるほどに伝わってくるだろう。詩集論であると同時に詩人論であり、詳細なるガイドブックであり、不思議だが人生論集でもあると感じられた。
「92年目の谷川俊太郎」が「ユリイカ」(青土社)の臨時増刊号として出た。詩とそれにまつわる書き手のみならず、アーティスト、ミュージシャン、現代思想や行動学、理論生命科学…、実に豪華で多彩な人々が、この460頁を超える紙面に原稿を寄せている。
分厚い雑誌の手触りはこれほどの「追っかけ」があることを今さらながら知らされることになる。前半に掲載されている、伊藤比呂美、尾崎真理子、高橋源一郎、マーサ中村、四元康祐による、谷川作品をめぐるシンポジウム「今更、谷川俊太郎」(早稲田大学で開催されたイベントの採録)に惹かれた。タイトルの「今更…」の語感が面白い。「今更」であり「今更」ではない一つ一つについて、五人の軽妙かつ深いトークが繰り広げられている。
伊藤はある時に谷川から「おれ、全然批評されてないの」と聞いたことがあった。たくさんの人々を動かしている本人による謎ですらある言だが、高橋は解き明かして「谷川さんの詩では、根本的に時間軸はなく、いつも空間軸を基に動いています。一方で現代詩って時間軸が基準だったように思うんですよね」と語っている。「そもそも批評は時間軸を相手にするものだから。だから谷川さんについての批評がなかったというのは、谷川さんにとって実感だったと思うんです」と。先に紹介した尾崎からは、「自分はジグソーパズルの一片一片を詩にしている感じがするんだよね」「僕が書いているのはきっと曼荼羅なんだ」と谷川が語ったエピソードも続けて紹介されている。
中ほどでは日本近現代文学者の加藤邦彦が「詩集の多さがかえって谷川俊太郎という詩人を捉えにくくしてしまっている面もある」と論考で述べている。先の山田の書物の序文にあった「谷川宇宙」という言葉を引きつつ「詩集が増えれば増えるほど、あまりに広大な谷川宇宙の全体像がみえにくくなってしまうのである」と説明する。「アンソロジーを含めて数多くの詩集が存在することで、谷川の詩には同一作品に複数の本文が成立してしまっている」ともその先で付け加えている。研究者としての悩ましさは察するに深刻な様子である。「いったい、どの本文に依拠して谷川を研究すれば良いのか」と。ジグソーパズルあるいは曼荼羅の難しさが、思わぬ形でここに出てきてしまっているのかもしれない。高橋の言を借りれば膨大な空間の詩人の成せる業であり、その全ては谷川徹三のフレーズを借用すれば今もなお増大する〈一巻〉と呼べるものかもしれない。
谷川俊太郎・ブレイディみかこ/奥村門土(絵)『その世とこの世』(岩波書店)は昨年の暮れに刊行となり話題を読んだものである。イギリス在住のブレディの明快な文章に谷川が文章と詩で応答するというスタイルであるが、英国と日本の距離と時間を超えるようにして深いやりとりがなされていて、言葉と人生の様々な信号の交わし合いを味わった。初めのほうで谷川は「世間知らずの十代の私は、自分が生きている世界を人間社会としてよりも、コスモス(宇宙)という言葉で捉えていました。自分という存在を意識し始めた頃、私はまず自分のいる場所がどこか知りたいと思いました。」と語る。座標を初めから求め続けてきたことがここでも分かる。学校生活にしだいに馴染めなくなり、父の本棚から本を読み散らしていたエピソードを語りながら、ある時に「私の座標は限りない宇宙の一点にある」と納得した、と。
それについてブレディは詩人に大失恋した思い出を語りつつ座標は何よりも「うりゃあああああ、なんとかなる」と思い直す心の中にあると応答しており二人の個性が最初からはっきり見えるようで面白かった。「その世とこの世」に「あの世」が加わり、様々な視点と思想の座標軸が二人のやりとりから見えた。
刊行となったばかりの谷川俊太郎・伊藤比呂美『ららら星のかなた』(中央公論新社)は
前の書の静謐な語り口とは全く別で、軽妙に流れる言葉の川底から光りだす小石を拾い出すような心持ちで読んだ。伊藤が発するユニークな質問の数々はぜひ聞いてみたいがなかなか聞けないことばかりで、ズバリとした豪快さといおうか、そこに爽快さもある。「谷川さんってしれっとウソつけるんですか?」「5分で詩の書き方を教えてください!」「自分が死ぬのが怖いの?」「タメ口で付き合える人はもう、ひとりもいないんですか?」
「仏教のいいとこ取り」というタイトルの対話で、谷川は華厳経の魅力について「全部の存在が結びついて、網の目状になっていて、自分のその網の目状の中の一点だと思わせるところが、ぴったりくるんですよ」と話している。「自分が何をやろうが全世界につながっているという感覚ですね」。伊藤はアメリカに暮らしていた時は広大なる荒野を、日本(熊本)に戻ってきてからは河原や山を歩き、夜は星を見てという時間の中で、自分もまた自然の一部=要素であることを確かめてきた姿を語った。詩集「河原荒草」に描かれた様々な地と草の風景が浮かんだ。
「宇宙の一点」「網の目状の一点」、なるほど、宇宙はまた無限なる魂の網であるのだろうか。「宇宙はどんどん膨らんでゆく/それ故みんなは不安である」と青年の谷川は書いたが、今もなおの谷川コスモスの増大がある。ますます研究者の「みんな」を不安にするかもしれないが、相次いで刊行された書物を開きながら、「山頂を渉る巨大な足」とその背中を追いかける。「ほゞ方針立つ」と独り言ちたい。
(原稿提出 一一月 初旬)