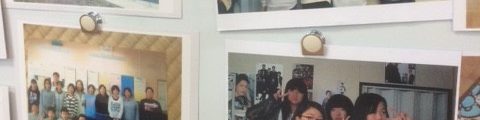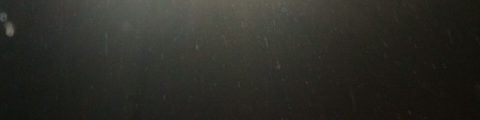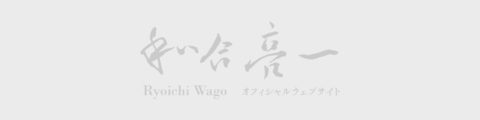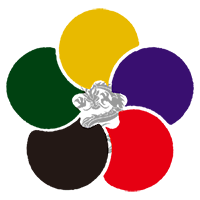〈追悼〉谷川俊太郎さん
寄 稿
雲の無い冬の空に祈る。
谷川俊太郎さんにはさすがに言えなかったが、息子の賢作さんに、言ってしまったことがある。谷川さんの詩集の総数を追い抜くのが目標です、と。それを聞いた賢作さんに「よし、いいぞ、抜け抜けーっ。」と勢いよく励まされたことを思い出す。
六六冊の詩集を世に残して谷川さんは旅立たれてしまった。私は最近に二六冊目の詩集を出したばかりである。道は遠い。果てしない…。(賢作さん、やはり無理です)。
去る一一月二〇日。新聞各紙は一面で訃報記事を大きく載せて谷川さんの死を悼んだ。「二十億光年の孤独」を代表作にあげている内容が多くあった。一八歳から一九歳の時の詩集が七〇年ほど後になっても代表作として紹介されることを当時は予想しなかっただろう。冬の不在の朝の空に一筋の雲。谷川さんの詩句が浮かぶ。「飛行機雲/それは芸術/無限のキャンパスに描く/はかない讃美歌の一節/(この瞬間 何という空の深さ)」。
三〇代から四〇代にさしかかる折に、谷川さんとの対談の機会を数多くいただいた。ゆくゆくは「日本語の話」(青土社・二〇一〇年)という一冊の対談集にまとめられることになったが、読み返してみると懐かしさと、若さと恥ずかしさで赤くなり、そして当時七〇代の頃であった谷川さんの元気な姿が様々に伝わってきて、目が潤む思いがする。完全に掌にのせられている感じがある。詩人の懐の大きさがあらためて伝わってくる。
谷川さんの創作方法について数多く質問している。フレーズが浮かぶ瞬間について様々に尋ねているところがある。「文字ではないですね。声になった言語という感じでしょうか。口に出さなくても、頭の中に声が出てくる、ということはあります」と冷静に語っている。詩作が進まない時にこの話しぶりを時折に思い出すことがある。
心理学者の河合焦雄氏とこのように述べているのも最近になって、谷川さんをめぐる本を読み直しながら見つけることができた。「言語レヴェルで考えるのではなく、言語以下というか、そういうレベルでモヤモヤ探っている、そのうちに釣り針に何かひっかかったみたいに、ぴょんと言葉が立ちあがってくる」。
こうした何かを「意識よりさらに深いところから出てくる何か」とも対談で幾度も語っていた。そこには十代の若者が飛行機雲に見とれて空の深さにはっとして立ち止ったかのような、心を射抜かれるような思いがけない「瞬間」と、大きなものへの畏怖と敬愛の念が溢れるほどに込められている感じがあった。詩を通してあらゆる〈深さ〉の位相と向き合っている。これらは意識下のそれであると同時にあらゆる事象が投げかける真理のそれである、と長年対話しながら感じてきた。あらためて驚かされるのは、こうした「そのうちに釣り針に」という法則性がまるで存在しない中で、六六冊の世界が産み出され続けたという事実である。
私のような若輩者でも、きちんと一人前に扱って下さる方だった。対談などでは、持ち前のユーモアと共に凛とした厳しさがあり、少しでも気の抜けた返球をすると甘えてはならないという感じで突き放されることも数多くあった。
それが実はとても怖かった。軽快でユニークな会話の中に呼吸の大きさと鋭さの両方をいつも突きつけられている印象があった。これら〈深さ〉についてはいつまでもたどりつけない詩作の境地であり、絶対に叶わないものであるとして憧れのような気持ちと共にいつも話しくれたが、しかし一方では、どこまでも実は測り終えていて、理知的に教えてくれているような印象があった。
最後の対談は二年前の春だった。残念ながらオンラインだった。会場まで足を運ぶ自信が無い…、と。画面上だったが元気なご様子だった。いつか、お宅にお伺いして、ご挨拶させていただきますとモニター越しに心を込めてお別れをした。それが最後になってしまった…。静かに冬の空を見あげる。雲が無い。光が降る。途轍もなく深いところへ、詩人は行ってしまった。